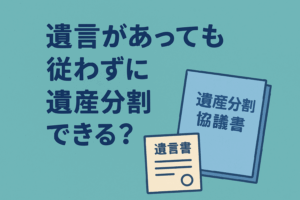相続税対策について
「相続税の対策は早めに!」
多くの方がそう聞いたことがあると思います。
実際に、相続税対策は長期的な計画で行うことが最も効果的です。
しかし、まだまだ元気だと思っていたけど急に病気が見つかって余命宣告された等の理由で、急な相続税対策が必要となる場合もあります。
そこで今回は、亡くなる直前でもできる相続税対策を、項目ごとに分けて解説します。
1.死亡保険金の非課税枠を活用する
生命保険金には、相続税の非課税枠があります。
非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数
たとえば相続人が3人なら、
500万円 × 3人 = 1,500万円 までが非課税になります。
仮に相続税率が20%とすると、1,500万円を預金から生命保険に変えるだけで、相続税が300万円も下がるので、これを使わない手はありません。
生命保険は、いつ契約しようが、亡くなった日時点でその契約が存在していれば非課税枠を使うことができます。契約から死亡までの期間が短くても関係ありません。
現在生命保険の非課税枠の限度まで使い切っていない方はぜひ検討してみましょう。

わしゃもう85歳だし持病もあるのにこんな状態から入れる生命保険なんてあるわけないじゃろ!
最近は、90歳まで加入できて、健康状態等の告知義務がない生命保険も存在します。
入院中ですと加入できませんが、自分は加入できないと思っていても実は加入できる場合もあるので、一度専門家に相談してみてください。
2.生前贈与を活用する。
相続人に対する贈与は、亡くなる直前7年以内のものは相続財産に足し戻す必要があります。(生前贈与加算)
つまり、相続人に対して亡くなる直前に贈与しても、結局相続税の対象となってしまうので効果はないのです。
ここでポイントとなるのは、生前贈与加算の対象は、相続人に対する贈与に限定されている点です。
つまり、孫や相続人の配偶者に対する贈与は生前贈与加算の対象にはならないので、なくなる直前の贈与でも相続税対策として機能します。
110万円を超えると、贈与税の申告が必要となるので注意が必要ですが、相続税の税率より贈与税の税率が低い場合には贈与税を支払った方が得となるケースもあるので、実際の贈与額を決める際は相続に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
また、相続人に対する贈与であっても、生前贈与加算の対象とならない特例贈与もあります。
それが、
(1)贈与税の配偶者控除の特例(いわゆる「おしどり贈与」)を受けている財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
(2)直系尊属から贈与を受けた住宅取得資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(3)直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(4)直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
この4つの制度を利用した贈与に関しては生前贈与加算の対象とはなりません。
ただし、(1)のおしどり贈与特例は使うとむしろ損してしまうケースも多い(別記事で後日解説します!)、(3)の教育資金贈与はもらった側が学生でないと相続財産になってしまう等、注意点も多々あるので、実際にこれらの制度を利用する際は税理士へ必ず相談しましょう。
3.お墓・仏壇・仏具を購入する。
お墓・仏壇・仏具などは高額なものではありますが、相続税の課税対象外です。
まだ購入してないのであれば生前に購入しておくと、現金が減る分相続財産が少なくなります。
亡くなった後で相続人が購入しても、その購入費用は葬儀費用として相続財産から引くことはできないので注意しましょう!
こういう場合はどうでしょうか。

そうじゃ!仏具は全部純金製でそろえようかの!これで相続財産がたっぷり減って相続税も安くなるわい!

純金でできた仏具は投資用とみなされるので、残念ですが相続税の課税対象外にはなりません!

残念じゃのう、、、
お墓・仏壇・仏具は基本的には相続税の課税対象外ですが、一般的なものよりはるかに高額な場合には課税対象となるので注意しましょう。
4.養子縁組を検討する
孫や相続人の配偶者と養子縁組を行うという方法です。
養子縁組を行うと、法定相続人が一人増えるので、生命保険の非課税枠や基礎控除が増加します。また、相続税は相続人の数が多いほど有利な計算になる仕組みになっています。そのため、少々強引な手段ですが養子縁組を行うことで相続税を減少させることができます。

でもそんな強引な手段で相続税を安くすると後で税務署から叱られるんじゃ、、??
もっともなご不安ですが、相続対策の養子縁組が無効かどうか争われた事件で、最高裁判所は「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものである」とし、「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と判示しました。(最三判平成29年1月31日)
長々とよくわからないことを書いていますが、要は相続税対策のために行われた養子縁組でも無効にはならない!ということです。
しかし養子縁組をする上でいくつか注意点があります。
(注意点1) 養子が法定相続人になれる人数には限度がある
被相続人に実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人が限度となります。

孫5人全員を養子にしたら相続税ゼロじゃわい!!
みたいなことはできません。
(注意点2) 孫を養子にした場合には、その孫が払う相続税額が2割加算される
孫が相続人になると、相続税がかかる財産を一代飛ばして移すことができます。そうすると一回分相続税の支払いをまぬがれることができるので、課税の公平の観点から孫を養子にした場合には、本来の相続税額より2割加算されることになっています。(孫が支払う分だけです。)
(注意点3) 他の相続人とトラブルになる可能性がある
養子縁組を行うことによって、その養子縁組で相続人となった人にも財産を取得する権利が生まれます。そのため、元々の相続人との間で相続争いに発展することがあります。
そうならないように、生前にきちんと説明しておく、できれば遺言を書いておく等、相続争いを起こさないための準備が必要です。
最後に
今回は亡くなる直前でも実行可能な相続税対策を4つご紹介しました。どれも効果的な方法ではありますが、一歩間違うと逆に相続税が高くなってしまったり、贈与税がかかって損してしまうこともあるので注意が必要です。
相続税申告・相続対策については、岸和田の税理士法人木戸&パートナーズにいつでもご相談ください。様々なご家庭の相続税申告・相続対策をお手伝いしてきた税理士の木戸辰弥が皆様のご相談にお答えします。
何かあれば下記のお電話番号又はお問い合わせよりお気軽にご相談ください!
お気軽にお問い合わせください。072-432-1311受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでお問い合わせ