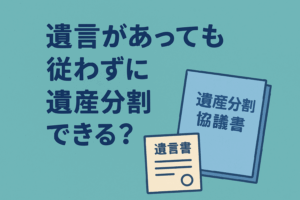相続税申告で見落としがちな「名義預金」とは?
大阪府岸和田市の税理士法人木戸&パートナーズ 税理士の木戸辰弥です。
皆さんは「名義預金(めいぎよきん)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
この名義預金、相続税申告の税務調査において、実は税務署がしっかりチェックしている要注意ポイントなんです。
名義預金とは、簡単に言うと「口座の名義人は家族になっているけど、お金の出どころや管理は被相続人(亡くなった方)だった」預金のことです。
たとえばこんなケースです。

昔作った息子と孫の名前の通帳があるからそれに毎年110万ずつ入れておこうかの、、
110万の贈与だから贈与税もかからないし相続税も減って一石二丁じゃわい!
子ども達にはわしが死んだときにビックリさせるために内緒にしておこうかのう
10年後・・・・

亡くなったおじいちゃんのタンスからぼくたち名義の預金通帳が出てきたよ!
しかもこんなにいっぱいお金が入ってるなんて、、
天国のおじいちゃんありがとう....

はい。その預金口座は名義預金ですね。
おじいさんの相続財産として相続税が課税されます!!

えええええええええええええ!!!!!??
このように、子どもや孫名義の預金通帳に入っているお金にも関わらず、亡くなった人の財産として相続税が課税されてしまうのです。
名義預金とみなされないためのチェックポイント
名義預金かどうかは、大きく分けてふたつのポイントにより判断されます。
まずひとつが、
その通帳と印鑑を誰が管理していたか(通帳の名義人がそのお金を自由にできる立場にあったか)
ということです。
上の例だとおじいさんは子ども達をびっくりさせるために、預金の存在を明かさず、通帳と印鑑も自分自身で管理していました。
これではそのお金は実質的におじいさんのものであったと認定されてしまいます。
もうひとつのポイントは、
あげた側もらった側の両方が贈与があったと認識していること です。
贈与は、贈与者(おじいさん)と受贈者(子どもと孫)の双方が、お金をあげた・お金をもらったと認識していないと成立しません。
上の例だと、おじいさんは子ども達にお金をあげたと認識していますが、子ども達はその事実を知らないので贈与が成立していないのです。
そうなると残念ながら名義預金としておじいさんの相続財産となってしまいます。
名義預金と認定されないためにしておくこと
では名義預金と認定されないようにするためにはどうしたいいのでしょうか。
名義預金とされないようには以下のようにしましょう。
1.贈与契約書を作成する。
まず一番重要なのは、贈与契約書を作成することです。
googleやYahoo!で「贈与契約書 ひな形」等と検索すればひな形が出てくると思うので、それを使って作成するのが一番手っ取り早いと思います。
贈与契約書を作る上で注意していただきたいのは、
贈与者・受贈者どちらも直筆で名前を署名すること
です。印鑑はハンコがあれば誰でもつけますが筆跡をごまかすことは難しいので、何よりの証拠になります。
(契約書に押す印鑑は実印でも認印でもどちらでも構いません。)
また、110万円を少し超える金額を贈与して、あえて贈与税の申告を行うことによって贈与の証拠とする方法等もよく紹介されていますが、これはあまり良い方法とはいえません。
なぜなら、贈与者が勝手に申告書を出しているというパターンがあり、完全な贈与の証拠とはいえないためです。
2.もらった人が通帳と印鑑を管理しておく。
そのままです!もらった人に通帳と印鑑を渡して、もらった人が自由にそのお金を使うことができるようにしておきましょう。
税務調査になると通帳やハンコがどこにあったかについて絶対に確認されるので、できるだけ早い段階で子どもや孫に通帳と印鑑を渡しておきましょう。

息子はいいとして孫はまだ10歳じゃぞ!そんな大金の管理なんてさせられるわけないじゃろ!
それはおっしゃる通りです!
もらった人が未成年の場合には、その未成年者の親に通帳と印鑑を渡して管理してもらうようにしましょう。
ただし、その未成年者が成人(18歳)になったタイミングで本人が管理できるようにしないといけません。遅くとも社会人になったタイミングで本人が管理できるようにしておきましょう。
最後に
名義預金は、形式ではなく「実質」で判断されるものです。
相続税の申告では「これは誰の財産か?」を、税務署と真っ向から問われることもあります。
「これは家族の名義だから大丈夫」と思っていても、調査で否認されてしまっては後の祭りです。
ご不安のある方は、岸和田市の税理士法人木戸&パートナーズにいつでもご相談ください!